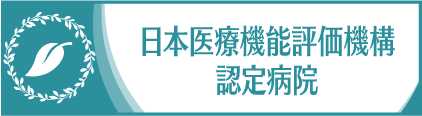小牧市民病院臨床研修プログラム
Komaki City Hospital Clinical training Program
小牧市民病院初期臨床研修プログラム規定
Ⅰ.プログラム名称
小牧市民病院初期臨床研修プログラム(以下プログラムと略す)
Ⅱ.プログラムの特徴
当院は、尾張北部医療圏における急性期医療の基幹病院としての役割を果たしているDPC特定病院群の総合病院である。救命救急センター、地域中核災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けており、平成24年5月には緩和ケア病棟も併設している。
臨床研修病院、日本病院機能評価認定病院に認定され、救急車の搬送数も年間約6500例と多く、初期研修医がファーストタッチで経験できる症例数は豊富である。
地域医師会との病診連携を推進しており、紹介率は40%、逆紹介率も60%を越えて、地域医療支援病院を目指している。
研修は2年間の総合診療方式で、特に救急医療に重点を置いている。(1年次、2年次ともに、1ヶ月間の救急科を必須としている)
1年目に救急科、脳神経外科、整形外科、小児科、緩和ケア科を必須科として、救急医療が不安なく対処でき、また、ターミナル・ケアを経験することで全人的な医療が早期に体得できるようにしている。
更に、病理・検査部門のローテーションも必修とし、不十分になりがちな検査方法の習得を学習できる。
関連大学の各医局とは緊密な連携関係にあり、本プログラム終了後に受ける卒後専門教育と一貫性を持つよう構成されている。
Ⅲ.プログラムの目標
研修の目標は、医師としての人格を涵養し、医学・医療への社会的ニーズを認識しながら、プライマリ・ケアに即応できる基本的臨床診察能力を習得し、最善の医療の提供ができるようになることである。
さらに医師としての社会的責任を自覚し、他部署とのチーム医療の重要性を理解し、疾病と関わる社会的因子への洞察力を養うことである。
具体的な項目として
- 臨床医に求められる基本的診療に必要な態度・技能・知識を習得する。
- 救急医療に求められる効率的で即応的な診察能力を習得する。
- 慢性疾患・高齢者・機能障害患者のための回復医療に必要な医学知識の習得と、その背景に存在する社会的・心理的病因を把握する。
- 患者・家族との良好な対人的関係が構築できる。
- 病院理念の「安全で安心な病院」の一員として、患者安全・医療安全を最優先事項と認識して行動する。
- チーム医療における他の医療メンバーとの良好な協調関係を確立して、「恕」の心で人格の涵養に努める。
- 地域医療の重要性に対する理解とともに診療所・病院間の連携を適切に実行できる習慣を身につける。
- 院内感染を含めた臨床における衛生管理に関わる知識を習得する。
- 研修体験を通じて社会が求める医師としての姿勢(接遇、インフォームド・コンセント等)を学び、第三者の評価を受け入れた上で客観的な自己評価・管理ができる能力を持つ努力を怠らない。
- 常に最先端の医学的知識の習得を心掛け、最善の医療の提供に努める。
Ⅳ.研修管理委員会・指導医部会・臨床研修センター
- 研修医がプライマリ・ケアに即応できる基本的臨床診察能力を習得し、最善の医療の提供ができるよう、臨床研修の充実のため、【研修管理委員会】(以下「委員会」)を設置する。
- 委員会は、初期臨床研修プログラムの立案、作成、管理、運営、研修の採用・中断・修了を含めた研修の評価、臨床研修の統括管理、その他研修に関する事項の検討を行う。
- 委員会の下部組織として、臨床研修指導医講習会を受講した指導医数名と、研修医代表で構成される【指導医部会】を置く。
- 委員会は研修管理委員会設置要綱に基づいて運営される。
- 当院における初期臨床研修を充実させるため【臨床研修センター】を置く。 設立 平成27年4月1日
- 病院組織上は病院長の直轄とし、初期臨床研修医(以下「研修医」)は、臨床研修センターに所属するものとする。
- 研修管理委員会の指導の下、研修医の研修をサポートしていく。研修に関する事項を討議し、研修管理委員会に諮り、承認を受け、実行する。
- 臨床研修センターには事務担当者を置く。
Ⅴ.プログラム責任者・副プログラム責任者
- プログラムを統括するプログラム責任者を置く。
- プログラム責任者は、プログラム責任者養成講習会を受講した者の中から院長が任命する。
- プログラム責任者は、プログラムの企画立案、実施の管理、研修医ごとに目標達成状況を把握し、研修医に対する助言、指導、その他の援助を行い、すべての研修医が目標を達成できるように指導、調整を行う。
- プログラム責任者の業務補佐の目的で副プログラム責任者を随時数名置く。
Ⅵ.研修実施責任者
- 協力型臨床研修病院において、当該病院の臨床研修を管理するものとして、研修実施責任者を置く。
- 研修実施責任者は、委員会の構成員となる。
Ⅶ.選任指導医・研修指導医・専任上級医・上級医・指導者
すべての職員が研修医をそだて上げる意識、自覚を持って指導に参画する。
1)専任指導医
- 専任指導医は、プログラム責任者が、厚生労働省認定の臨床研修指導医講習会を受講している者から、研修医ごとに選出する。
- 専任指導医は、2年間の初期研修期間に亘り、公私を分かたずに指導にあたる。
- 専任指導医は、担当研修医と年2回以上の面接で、進路相談、メンターを担う。
2)研修指導医
- 各科の指導医は、7年以上の臨床経験を持ち、臨床研修指導を行うために必要な経験・能力を備えた者全員で、研修指導にあたる。
- 指導医は、研修医による診断・治療と、その結果について直接の責任を負う。研修医の記載記録・内容を確認して承認するとともに指導内容を診療記録に残す。
- 指導医は、担当する分野における研修において、研修医の研修目標が達成できるよう指導する。研修終了後に研修医の評価をプログラム責任者に報告する。
- 指導医は研修医の身体的、精神的変化を観察し、問題の早期発見に努め、必要な対策を講じる。
- 指導医が不在になる場合は、指導医の臨床経験に相当する医師を代理指名する。
3)専任上級医
- 専任上級医は、プログラム責任者が、2年以上の臨床経験を有する医師から、研修医ごとに選任する。
- 専任上級医は、研修期間の半年の間に亘り、公私を分かたずに指導にあたる。(延伸を妨げない)
- 専任上級医は、担当研修医と半年に1回以上の面接を行い、進路相談、メンターを担う。
4)上級医
- 上級医は、指導医の補佐を担当する。
- 上級医は2年以上の臨床経験を有する医師で、指導医の管理の下に、臨床の現場で研修医の指導にあたる。
- 上級医は、研修医の診断・治療・記録等を監査して、指導内容を診療記録に残す。
5)指導者
- 指導者は、看護部・薬剤部・他のコメディカル部門の職種から選任された研修管理委員会の委員により、指名される。
- 指導者は、研修医を評価し、プログラム責任者に報告する。
Ⅷ.指導体制
- 研修医は、年間計画に従って、各科に配属され、科の指導責任者の総括のもとに、研修プログラムに添って研修する。
- 各科の「研修目標」は必ず達成する事が求められる。
- 各科ローテーション期間中、各科が単独で対応・解決困難な事例が発生した場合、研修管理委員会に協力要請の報告をして、解決にあたる。
Ⅸ.協力型臨床研修病院・臨床研修協力施設
1)精神科
- 東尾張病院(協力型臨床研修病院) 病床数:233床
診療科:精神科、神経科、内科、歯科 - 東春病院(臨床研修協力施設) 病床数:297床
診療科:精神科、内科、歯科 - もりやま総合心療病院(協力型臨床研修病院) 病床数:490床
診療科:精神科、神経科、心療内科
2)地域医療
-
千秋病院(協力型臨床研修病院) 病床数:294床(一般病床 150床、療養型病床 144床)
診療科:内科、外科、整形外科、脳神経外科、眼科、泌尿器科、肛門科、小児科、皮膚科、 放射線科、リハビリテーション科、リウマチ科、歯科 -
白山リハビリテーション病院(臨床研修協力施設)病床数:84床
診療科:リハビリテーション科、内科 -
サンエイクリニック(臨床研修協力施設) 病床数:0床
診療科:内科
Ⅹ.研修の種別・期間・開始時期
- 研修は、医師法第16条の2第1項に準拠し、研修を受けるものは医師国家試験に合格し、医師免許を有するものでなければならない。
- 研修期間は原則2年間であり、4月1日より開始する。
ⅩⅠ.研修の募集・定員・申し込み・選考・採用・中断と再開
1)募集
「医師法第16条の2第1項に設定する臨床研修に関する省令の施行について」に従い、募集について ホームページ等に掲載し、全国から広く公募(マッチング利用)する。
2)定員
- 研修医の定員は、「医師法第16条の2第1項に設定する臨床研修に関する省令の施行について」に従い、研修管理委員会にて協議し、定員を決定する。
- 協力型臨床研修病院としての研修、研修未修了者の研修再開等については、研修管理委員会にて協議、判断のうえ、受け入れを行う。
3)申し込み
研修希望者は、採用試験申込書の書類を添えて所定の期日までに病院へ提出する。
4)選考方法
- 面接・筆記(小論文)
- 面接を担当する選考者は、院長が指名する。
- 選考結果に基づき、院長の承認を得て、医師臨床研修協議会の実施する研修医マッチングに登録する。
5)採用
- 研修医の採用は、マッチングの結果を受け、受験者に通知する。
- マッチ者が採用予定人数に満たない場合は、協議会のルールに従い、二次募集を実施する。
- 研修医として採用されたものは、承諾書(別紙様式)を所定の期日までに院長に提出する。
6)中断および再開
- 委員会は、臨床医としての適正を欠く場合、妊娠・出産・傷病・キャリア形成などで研修医として研修継続が困難であると認める場合には、その時点での研修評価を行い院長に報告する。
- 院長は、 1の報告または研修医の申出を受けて、研修を中断することができる。
- 研修医の臨床研修を中断した場合、院長は速やかに該当研修医に対し、医師法第16条の2第1項に基づき、臨床研修中断証を交付する。
- この場合、院長は当該研修医が納得する判断となるよう、臨床研修に関する正確な情報を十分に把握することに努め、他の研修病院を紹介する等、臨床研修再開のための支援を行う。
- 中断した研修医が研修を当院で再開希望する時には、中断内容を考慮し可否を決定する。また臨床研修中断証の内容を考慮した研修を行う。
XⅡ.研修医の身分・所属
- 身分:嘱託職員
- 所属:臨床研修センター
XⅣ.研修の方法
研修方法は当院臨床研修プログラムに基づいて行う。
1)オリエンテーション
- 新入職員研修
- 初期研修医向け
- 病院概要、各種コメディカルの業務内容、医療保険の仕組みなど...院長、事務長、薬局長、看護 局長、放射線技師長、臨床検査技師長、臨床工学技師長、リハビリテーション技師長、医事課長 など
| 救急対応のノウハウ | 救急科はじめ各診療科指導医など |
|---|---|
| 初期研修医の心得など | 当院初期研修上級医・研修管理委員長・プログラム責任者 |
| 各委員会の講習会 | 医療安全委員会、院内感染対策委員会、輸血療法委員会、接遇研修など |
2)計画の作成
各研修医の要望を加味し、研修管理委員長・プログラム責任者、副委員長(副プログラム責任者)と研修医の間で調整し、時間割と研修医配置表を編成する。
3)ローテーション研修
2年間で、省令に定める「必修科目」の内科、救急部門、地域医療、「選択必修科目」の外科、麻酔科、小児科、産婦人科、精神科の全部を必修とする。
1年目に、救急科、脳神経外科、整形外科の3部門を救急部門としてローテーションし、小児科 も研修することで、救命救急医療が不安なく対処できるようにしている。
また、病理部門・検査も必修とし、各科ローテーション中では、不十分になりがちな検査の実施 方法の習得、超音波診断の実践方法を集中して学習し、診断能力向上を図る。
また、緩和ケア科も必修として、ターミナル・ケアを経験することで、全人的な医療が早期に体得できるようにしている。
以下のローテーション研修を行う。(1ヶ月を1単位とする。)
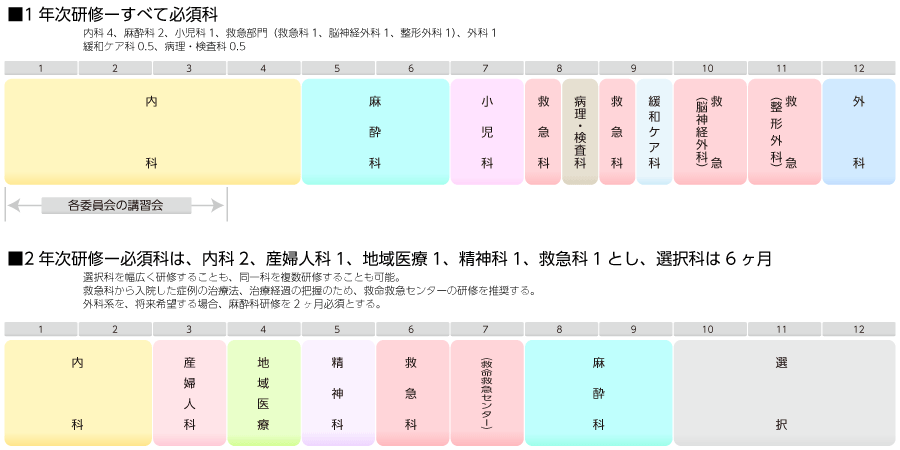
※画像を押すと拡大表示されます。
4)救急診療
プライマリ・ケア修得の最優先業務として位置付けており、1年次・2年次を通して、日常よく遭遇する疾患については自力で対処できる基本的な知識と技術を養う。時間内の救急患者は救急科指導医と各科ローテーション時の担当医(救急担当医、主治医)の指導のもとで研修する。
5)研修医の当直業務
-
時間外救急患者は当直業務として行い、1年次の当直は連日2名体制で、各当直医と2年次研修医の監督のもとで当直研修する。
2年次の当直は、4月から9月の期間および休日は2名体制で、10月から1名体制となり、各当直医の監督のもとで当直研修するとともに、1年次の指導にあたる。また4月の1ヶ月間は、1名が、1年次当直医の指導サポートとして、17時15分から22時まで勤務する。 - 原則的に週一回程度の当直を担当する。
- 研修医当直勤務に関する諸規定は「救命救急センターマニュアル」に定める。
- 当直明けは、原則として全日勤務免除とする。
6)協力型臨床研修病院・臨床研修協力施設
精神科研修は、「東尾張病院」と「東春病院」、地域医療研修は、「千秋病院」と「白山リハビリテーション病院」と協力し充実した研修をめざす。
7)その他教育に関する行事
- 基本的臨床能力評価試験(原則として全員参加)
- 研修医教育講座:毎週火曜日 17:30から
- 医局会主催による各科輪番制の症例検討会
- ローテーション各科の症例検討会、抄読会、カンファレンスなど
- 化学療法委員会のキャンサーボード
- 緩和ケア研修会
- 病院全職員を対象とした全体講演会・各種委員会の勉強会
- 病院全職種による院内学術集会(毎年秋に開催)
- 救急救命士とのICLS研修(年3回開催)
- 救急症例検討会(CPA症例も含む)
- 臨床病理検討会(CPC):医局会での発表担当
-
各診療科指導医のレクチャー
これらに積極的に参加する。
8)研修計画の変更
目標達成が不十分な時、専攻科決定などの理由により、研修の計画変更が必要な場合には、研修管理委員長・プログラム責任者に申し出て、研修期間を調整することができる。
研修管理委員長・プログラム責任者は、他の研修医・関連科指導責任者の調整を図る。
XⅤ.研修医が行える医療行為・責任・守秘義務など
- 研修医は、指導医の指示監督の下、別に定める医療行為に関する基準に基づき診療を行う。
- 前項に基づいて実施した研修医の医療行為に伴い生じた事故等の責任は、当院が負う。
- 研修医は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様である。 (守秘義務)
XVI.研修医代表者、各種委員会の研修医代表および委員会などへの出席
1)研修医は各年次毎に代表者をおく。
2)代表者は、研修医間で互選する。
3)研修管理委員会が指定したメンバーは、下記の委員会に参加する。
- 研修管理委員会(指導医部会)
- 医療安全委員会
- リスクマネージャー会議
- 院内感染対策委員会
- 地域連携室運営委員会
- 倫理委員会
- 臨床研究倫理審査委員会・治験審査委員会
- 医療情報システム室 全体会
- 栄養委員会
- NST委員会
- 化学療法委員会
- キャンサーボード
- 輸血療法委員会
- 保険医療検討委員会
- DPC委員会
- 業務検討委員会
- 救命救急センター運営委員会
- その他、院長、各委員長が必要と認めた委員会
4)各代表者は、他の研修医へのフィードバックを行う。
XⅦ.病院行事への参加
以下に揚げる病院行事・業務には、可能な限り参加しなければならない。
- 研修医勧誘のための説明会(名古屋、東京、大阪で開催予定)
- 病院主催の市民公開講座など
- その他病院行事(災害訓練など)
- 災害時
XⅧ.研修中の心のケア・相談
各指導医、各上級医、指導者、実施責任者は、研修医の身体的、精神的変化を注意深く観察し、問題の早期発見に努めなければならない。
①ストレスに対する気づき
②リラクゼーションのアドバイス
精神科医による年1回の定期メンタルヘルス相談あり。そのほか、随時相談に応じる体制あり。(原則、プログラム責任者へ報告する。)
XIX.研修の記録および評価方法
1)研修の記録・評価
研修医は、院内の電子カルテ及びEPOCを利用して、臨床研修についての記録をし、評価を受 ける。
研修医は各科のローテーション中、適宜、自己記録、目標記録、レポートをもとに形成的評価(フィードバック)及び総括的評価を受ける。
- ローテーション内容(臨床医としての適正の評価) ローテーション研修終了後、研修医・指導医・指導者はEPOCの行動目標項目を入力するとともに、各科の研修目標チェックリストに評価点を記入し、臨床研修センターに提出する。 研修管理委員会はその内容を確認し、研修の進捗状況を把握する。入力された評価内容と提出されたチェックリストは、研修医別に集計管理するとともに、研修の進捗状況を研修管理委員会にて点検する。また、2年目終了時に全ローテーション評価がされているかを研修管理委員会にて確認し、研修修了の判定を行う。
- 経験症例等(厚生労働省の示す「臨床研修の到達目標」の必須項目等) 研修医・指導医は各ローテーション終了時、EPOCの経験目標項目を入力する。 入力されたデータを研修医別に集計管理するとともに、研修の進捗状況を研修管理委員会にて点検する。また、2年目終了時に厚生労働省の示す「臨床研修の到達目標」の必須項目を達成しているかを研修管理委員会にて確認し、研修修了の判定を行う。
- 症例レポート(必須症例レポート等) 研修医は、必要な症例レポートを作成し、指導医にコメントをもらい、指導医コメントが記載されたものを臨床研修センターに提出する。レポートの様式は、内科学会認定医取得時の申請用紙に準ずるものとする。 原則として、1課題1レポートとし、1症例を複数のレポートにしないこと。 また、担当した入院患者の「入院概要録」を積極的に記載し、指導医の認証を受けて、臨床研修センターに提出する。 提出されたレポート・概要録は研修医別に集計管理するとともに、研修の進捗状況を研修管理委員会にて点検する。また、2年目終了時に必要な症例のレポートが提出されているかを研修管理委員会にて確認し、研修修了の判定を行う。
- CPCを担当した研修医は、レポートを作成し、臨床研修センターに提出する。
| 評価項目 | 内容 | 評価者 | 総括的評価基準 |
|---|---|---|---|
| ①ローテーション内容 | 医師としての基本姿勢 診療態度・チーム医療 |
自己・指導医・指導者 | EPOCの要努力のC項目が1/2以下であることと、チェックリストの5段階評価で、2.5以上であること。 なお、C項目が1/2より多い場合や、チェックリストの5段階評価が2.5未満の場合は、研修指導医が直接指導を行い、記録を残すこと。 |
| ②経験症例等 | 経験した検査・手技 担当した(入院)患者の疾患・症例 経験すべき症例への対応 |
自己・指導医 | 厚生労働省臨床研修到達経験目標のB経験すべき症状・病態・疾患について経験するとともに、経験が求められる疾患・病態88項目のうち70%以上を経験すること。 |
| ③症例レポート | 担当した(入院)患者の疾患・症例 経験すべき症例への対応 |
自己・指導医 | 「臨床研修・症例レポート提出票」にて提出を義務づけている32項目のレポートを全て提出すること。 |
2)研修プログラム・研修カリキュラム・指導医・指導体制の評価
研修管理委員長・プログラム責任者は、研修プログラム、研修カリキュラム、指導医・指導体制に対する研修医からの評価を聴取し、その結果を研修管理委員会に諮り、研修システムの改善のためにフィードバックさせる。
また、研修の実績により評価項目・基準の見直しを研修管理委員会に諮り、実施する。
XX.判定・終了・進路
| 1)研修医が2年間の研修中は、形成的評価を行い、研修内容の改善を図る。 | |
| 2)2年間の研修を修了するにあたり、委員会において総括的評価を行い研修医の判定をおこなう。 | |
| ①研修実施期間 |
ア、研修期間を通じた研修休止期間が90日以内 イ、研修休止の理由は、妊娠・出産・育児・傷病などの正当なもの |
|---|---|
| ②研修目標の到達目標達成度 |
ア、厚生労働省の示す「臨床研修の到達目標」の必須項目 (研修の記録および評価方法における①経験症例等の総括的評価基準参照) イ、必須症例レポートの提出 (研修の記録および評価方法における②症例レポートの総括的評価基準参照) |
| ③臨床医としての適正の評価 |
ア、安心・安全な医療の提供 イ、法令・規則を遵守できる ウ、医療人としての適正に問題がない (研修の記録および評価方法における③ローテーション内容の総括的評価基準参照) |
| 3)研修修了基準を満たしたと判定された場合、院長に報告し、臨床研修修了証を交付する。 | |
| 4)委員会で、修了基準を満たしていないと判定された場合は、院長に報告し、未修了と判定した研修医に対して、その理由を説明し、臨床研修未修了証を交付する。 | |
| 5)未修了とした研修医は、原則として引き続き同一のプログラムで研修を継続することとし、委員会は、修了基準を満たすための履修計画書を東海北陸厚生局へ提出する。 | |
| 6)プログラム修了後は希望する専門科の状況に応じて、常勤医となることができ、後期専攻医カリキュラムに従い、更に専門的研修を続けることができる。 | |
XXⅠ.研修修了後のフォロー体制
当院での初期臨床研修での教育が適切なものであったか否か、教育病院としての責任が求められて いるため、その後、どのように活躍しているかを把握する必要がある。
- 当院は、修了者の名簿を作成する。
- 当院から連絡が取れるように、退職時には連絡先を報告する。
- 少なくとも、2年毎に連絡先へ近況報告の依頼をし、就職先の確認をとる。
XXⅡ.研修記録の保管・閲覧
-
研修医に関する以下の個人情報、研修情報は、研修修了日(中断日)から5年間保管する。
①氏名、医籍登録番号、生年月日
②修了したプログラム名称、開始・修了・中断年月日
③臨床研修病院、協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設の名称
④研修の内容、研修医の評価
⑤中断した場合には中断の理由 -
臨床研修の記録のうちEPOCデータについては、プログラム責任者が管理する。 その他の電子データは、医療情報システム室で管理する。
①研修管理委員・事務局、研修医は研修記録を閲覧することができる。 ②研修記録閲覧の際には研修管理委員会委員長の許可の下、記載情報が臨床研修医の個人情報であることに十分留意し、慎重に取り扱う。
・小牧市民病院初期臨床研修プログラムPDF
専攻医(後期臨床研修)研修プログラム
当院が基幹施設として研修実施・専攻医を募集するプログラム
| 診療科 | プログラム | 連携施設 |
|---|---|---|
| 内科 | 小牧市民病院内科専門研修プログラム PDF |
春日井市民病院、東海中央病院、東濃厚生病院、 名城病院、公立陶生病院、名古屋大学、 藤田保健衛生大学 |
| 外科 | 小牧市民病院外科研修プログラム PDF |
公立陶生病院、名古屋記念病院、名古屋大学、 岡崎市民病院、東濃厚生病院、江南厚生病院、 西尾市民病院 |
当院が連携施設として研修実施・専攻医を募集するプログラム
| 診療科 | 基幹施設 | 診療科 | 基幹施設 |
|---|---|---|---|
| 小児科 | 名古屋市立大学 | 放射線科 | 名古屋大学 |
| 産婦人科 | 名古屋大学 | 皮膚科 | 名古屋大学 中京病院 |
| 泌尿器科 | 名古屋大学 | 精神科 | 名古屋大学 |
| 脳神経外科 | 名古屋大学 | 救急科 | 名古屋大学 産業医科大学 |
| 整形外科 | 名古屋市立大学 | 麻酔科 | 名古屋大学 |
| 形成外科 | 名古屋大学 | 眼科 | 名古屋大学 |
| 耳鼻いんこう科 | 名古屋大学 | 病理診断科 | 岐阜大学 名古屋第一赤十字病院 |
 小牧市民病院
小牧市民病院(こまきしみんびょういん)
〒485-8520
愛知県小牧市常普請1丁目20番地
TEL(0568)76-4131
FAX(0568)76-4145
Email: kch-gen@komakihp.gr.jp