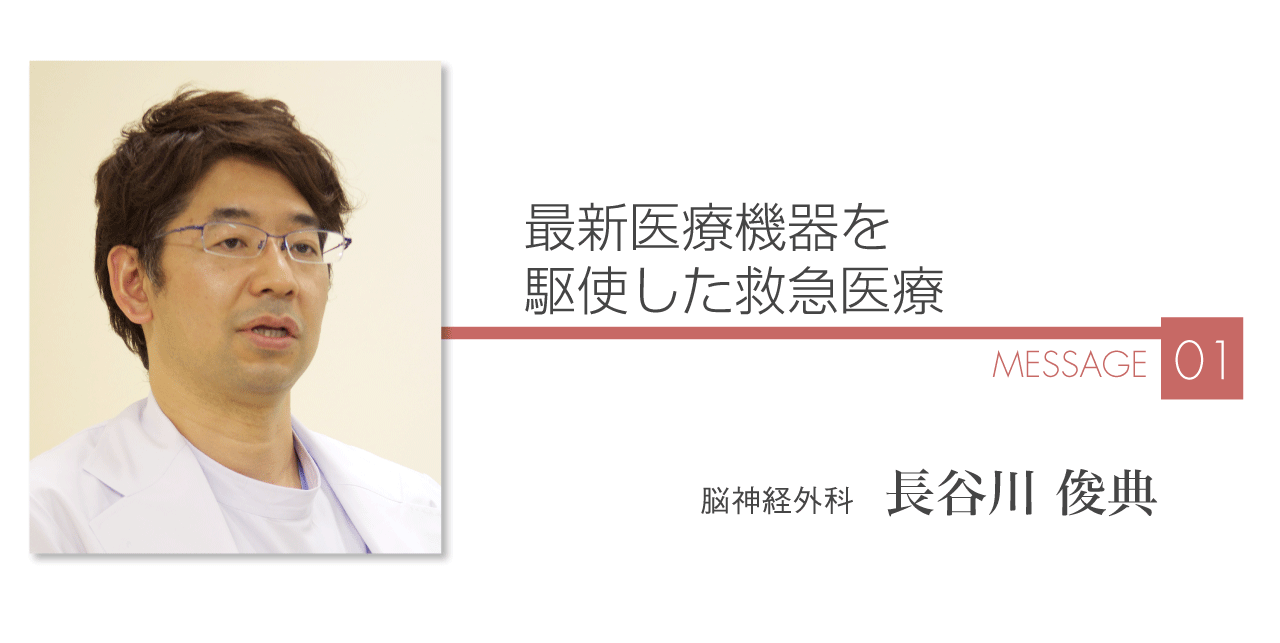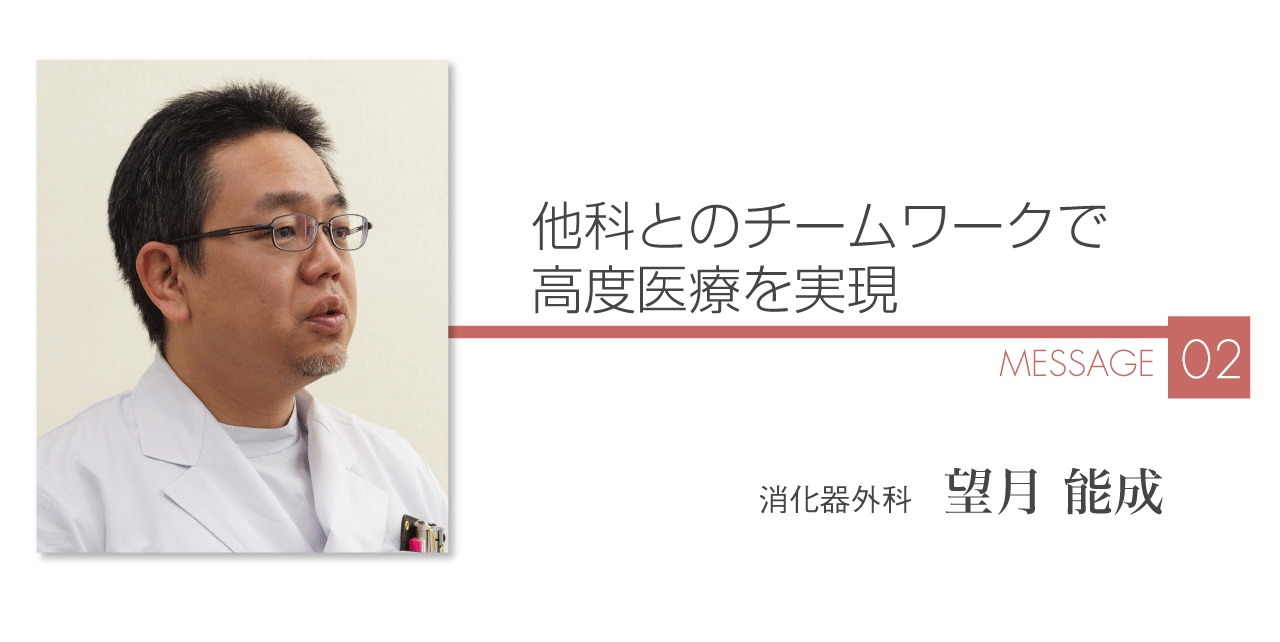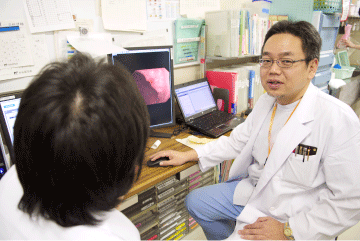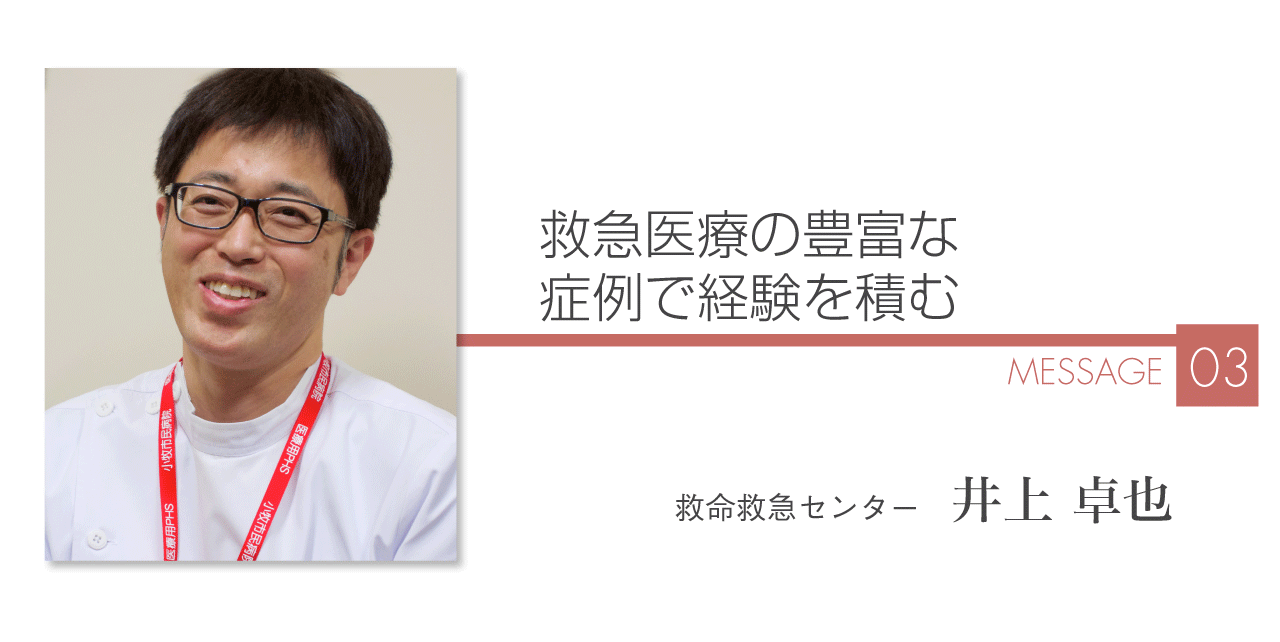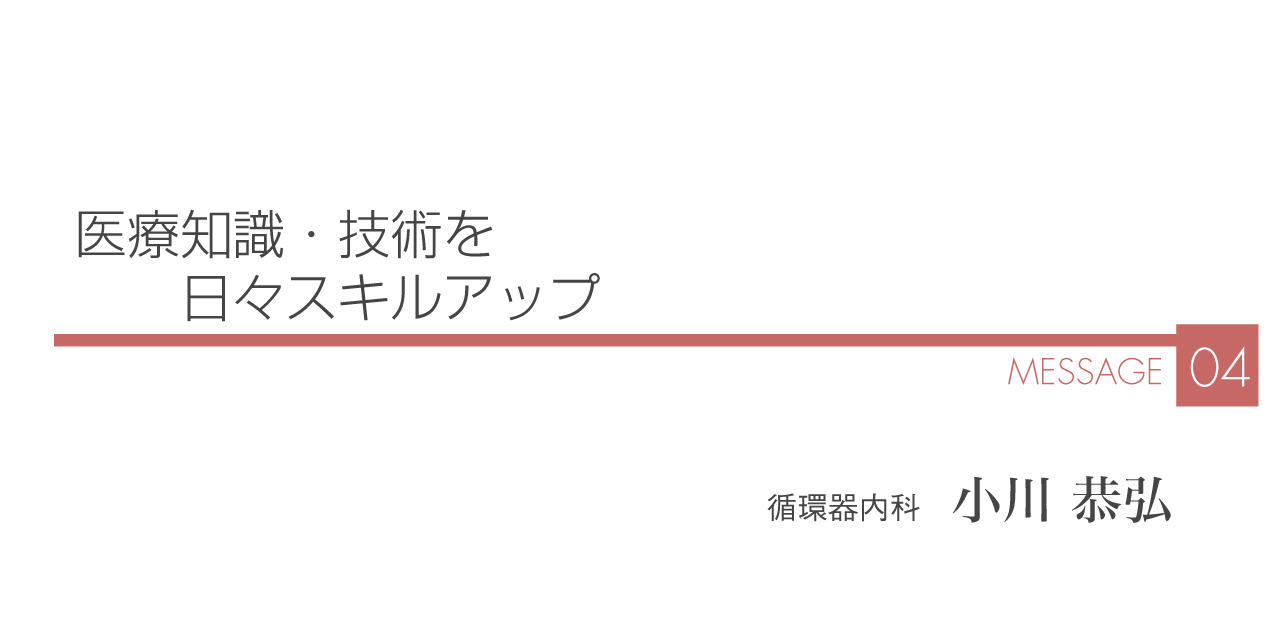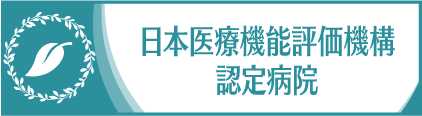0568-76-4131
〒485-8520 愛知県小牧市常普請1丁目20番地
 小牧市民病院
小牧市民病院(こまきしみんびょういん)
〒485-8520
愛知県小牧市常普請1丁目20番地
TEL(0568)76-4131
FAX(0568)76-4145
Email: kch-gen@komakihp.gr.jp